|
江戸時代慶応2年。西暦でいうと1866年ですから徳川慶喜が大政奉還を行なう前年に「待宵」は著されました。
著者は渡瀬荘次郎、棋聖として名を馳せた天野宗歩の門下生で四天王の一人です。渡瀬の著書ではありますが、詰将棋を実際に作ったのが渡瀬であるかどうかは疑問で、むしろ編者と見たほうが良さそうです。後に渡瀬が作る必死問題の数々を見るかぎり、詰将棋を作っていてもおかしくはなさそうですが……。
今回はその中から5題紹介いたしましょう。
[第1図]待宵第8番(5手詰)
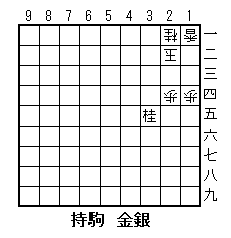
[第2図]待宵第1番(7手詰)
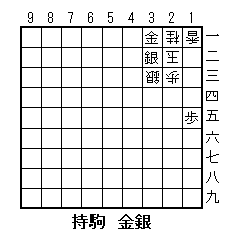
皆さんもどこかで一度はお目にかかっていると思います。実戦さながらに桂香を配し、小駒ばかりの簡素な形。思わず解いてみようという気にさせられる詰将棋です。
慣れてしまえば基本手筋に過ぎませんが、将棋を始めて間もない者にとってはそれなりに悩みの種になるようです。
第1図正解―23銀、13玉、12銀成、同玉、23金まで5手。
初手23金の紛れを見せておいて、打った銀をすぐに成り捨てる手順は盲点になりやすく、よく将棋の入門書などにも掲載されています。
第2図正解―13銀、同桂、12金、同玉、21銀生、22玉、32金まで7手。
初手21銀成の紛れが強烈で、以下12玉、11成銀、同玉、14香、13歩、同香生、22玉となってなんとか逃れているようです。13玉と逃がさないように攻めたいのにいきなり13銀とは初心者泣かせの問題ですね。入門書などには頭の2手を省いた5手詰で掲載されていることが多いようです。
[第3図]待宵第2番(5手詰)
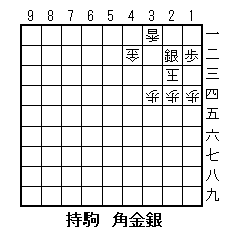
[第4図]待宵第5番(7手詰)
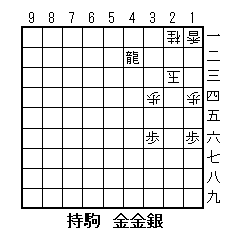
やや難しい問題です。
第3図正解―41角、同金、32銀、同香、13金まで5手。
角を捨てることによって退路封鎖と守備金の力を弱めます。そこで焦点の銀捨てが決め手となります。本作の12歩は興味ある配置で、この歩がない場合も「41角、同金、12銀、22玉、23金まで5手」といういようにきれいにまとまっているのです。作者が12歩を置いた理由、それはおそらく3手目の銀捨ての味に拘ったからではないでしょうか?
第4図正解―33金、同桂、13金、同香、12銀、24玉、22龍まで7手。
筆者自身、中学生の頃に大いに悩まされた作品です。その理由は手順前後に陥ったのと、4手目13同玉の変化にあります。以下33龍、23合、24銀、12玉、23龍まで9手駒余りとなり、現在でも許容範囲とはいえ悩ましいところ。時代を遡るほど「変化が正解より2手長く駒が余る=変長」に対して寛大であったようです。ここでは完全な実戦型に拘る作者の意地が出すぎたようで、例えば11香→12香程度でこの問題は解消できるようです。
[第5図]待宵第19番(7手詰)
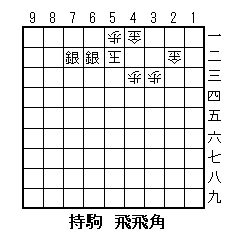
ここまでくると初心者には厳しすぎるほど難度が高いですネ。
第5図正解―32飛、同金寄、42飛、同金直、74角、62玉、63角成まで7手。
右に逃げられたらどうするか。こういう場合は右に捨駒をして取らせることで退路の封鎖ができることがあります。本作は初〜3手目と連続で飛を捨てる意外な構成で、飛車がかわいくて仕方のないヒトには永遠に解けない問題でしょう。
「待宵」をはじめとした、いわゆる古典の名作短編を見ていると、意外性のある手順、そしてあまりにも簡素な形に驚くことばかりです。「待宵」は特に実戦型が多く、後進の指導用教科書としての役割もあったのでは、と思われます。
無双、図巧もそうですが、江戸時代にこれほど完成度の高いものが作られていたのはある意味、奇蹟に近い現象なのかもしれません。
|