|
“回転率”というものがあります。
第1図は第7回のオモロ講座掲載の作品ですが、この回転率はどうなるのでしょうか?
その前に、本作の作意を復習しましょう。
[第1図]
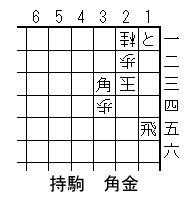
【正解】
24角成、同玉、51角、23玉、13飛成、同桂、24金、32玉、33金、31玉、42角成まで11手詰
△白人「回転率って、角や飛がグルグルと何回転するかという」
ことではなくて、使用駒数に対する手数の割合です。
第1図の場合、
11(手数)÷9(駒数)=122%
が、この作の回転率ということになります。
△白人「回転率は大きいほどいい?」
▲マニ夫「でもこれなんか、7手目からはダレとるやんケ。最終手も非限定(42金も可)やし…」
はい。くどいようですが、これもひとつの指標です。一般的に、使用駒が少ない割に手数の長い方が、詰将棋作家の目指すところかもしれません。
▲マニ夫「そうやない人も絶対おりまっせ!」
[第2図]
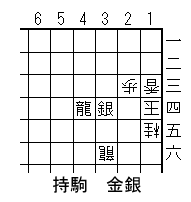
△白人「これは、どうなるの?」
この正解手順は
24金、同玉、25銀打、同龍、33銀生まで5手詰
(第8回オモロ講座より)
したがって回転率は、
5(手数)÷9(駒数)=56%
△白人「それじゃ、第2図の方が第1図よりも回転率が悪いということになるね」
▲マニ夫「しかし、第2図の方がピシッと決まっとるで」
△白人「僕は第1図の方が好きだなぁ。駒の打換え手筋も入っているし」
中身との相対評価になりますかね。
では第3図をご覧ください。これは、近代将棋、昭和41年5月号に掲載された、谷向奇龍氏の作品です。
[第3図]
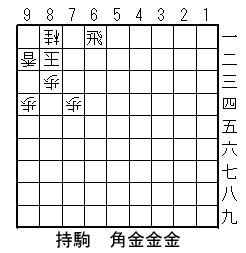
△白人「62飛成は93玉で逃げられちゃうねぇ。難しい!」
【正解】
71角、73玉、62角成、64玉、44馬(第4図)、73玉、63飛成、同玉、54金、73玉、62馬、82玉、72金、93玉、84金、同歩、71馬、83玉、82馬まで19手詰
[第4図]

さり気ない実戦型から、まさかという大技が飛び出します。大海へ逃がしそうな62角成から44馬がそれ。ここで75玉とする手は、66馬と引き戻して早詰です。
実戦型の名作と言えるでしょう。
△白人「7手目63飛成に、84玉と逃げるとどうなるの?」
▲マニ夫「それには75金という奇手があって、同歩に74金、95玉、77馬、86合、85金以下詰みや」(※)
△白人「「はぁ、流石だね」
本作の回転率は
19(手数)÷11(駒数)=173%
となります。
さて、では2月号からの復習をしておきましょう。
動駒率:動いた駒数/配置駒数
……多くの駒が動く方が良い。
消去率:消えた駒数/使用駒数
……捨駒が多いほど良い。
回転率:詰手数/使用駒数
……駒数の割に手数の長いほど良い。
となります。作る時も解く時でも、参考にしてみてください。
▲マニ夫「参考程度でエエ」
(※)75金、同玉、66馬、86玉、83龍、85飛合以下変化長手数順がある。今回転載するにあたって調べたところ発覚。既知かどうかは不明。
|